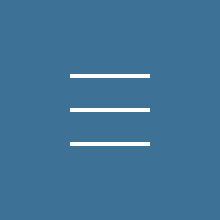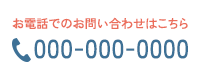胃炎とは
 胃炎は、胃の粘膜に炎症が起こることで発症し、症状の持続期間により「急性胃炎」と「慢性胃炎」に分けられます。
胃炎は、胃の粘膜に炎症が起こることで発症し、症状の持続期間により「急性胃炎」と「慢性胃炎」に分けられます。
急性胃炎は、過度の飲酒や香辛料・カフェインの摂りすぎ、喫煙、精神的ストレスなどが引き金となり、急激に強い症状を引き起こすことがあります。しかし多くの場合、胃腸に負担をかけないよう過ごすことで比較的短期間で回復が見込めます。
一方、慢性胃炎の主な原因は、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染です。その他、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)などの薬剤による副作用も一因となります。粘膜の異常が見られないにもかかわらず、胃の不快感や痛みが続く場合には、「機能性ディスペプシア」と診断されるケースもあります。
ピロリ菌による胃炎は、除菌治療によって症状が改善し、再発のリスクも大幅に軽減されます。ただし、放置された場合、炎症が進行して「萎縮性胃炎」に至り、胃がんの発症リスクが高まる恐れがあります。そのため、ピロリ菌感染が疑われる場合には、早期の受診が重要です。また、お薬の副作用が原因で胃炎を起こしている場合には、薬剤の見直しや変更が症状の改善に繋がることがあります。
機能性ディスペプシアについては、消化管の過敏性や運動機能の低下が影響していると考えられていますが、明確な病変が確認できないため、診断や治療が難しい場合もあります。
当院では、消化器病専門医が専門性の高い診療を行っており、患者様1人ひとりに合わせた治療の提案が可能です。原因不明の胃の不快感や痛みなどでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
急性胃炎・慢性胃炎(萎縮性胃炎)の主な症状
急性胃炎
- 胃痛
- みぞおち付近の不快感や痛み
- 胃の張りや重苦しさ
- 胸焼け
- 吐き気や嘔吐
- 黒く粘つく便(タール便)
など
慢性胃炎・萎縮性胃炎
- 胃痛
- みぞおちの鈍い痛みや不快感
- 胃がムカムカする
- 胃もたれ
- 胃が重く感じる
- 胸焼け
- 食欲がわかない
- 少量の食事でもすぐ満腹になる
- お腹の膨満感(張り)
など
胃の不調は、市販薬で一時的に和らぐこともありますが、疾患が潜んでいるケースも少なくありません。そのため、症状が長引いたり繰り返したりする場合は、自己判断せず、早めに消化器内科で診察を受けることが重要です。
また、家族に胃がんの既往がある方や、ピロリ菌陽性と診断された方が身近にいる場合、自身もピロリ菌に感染している可能性があります。
ピロリ菌による胃炎は、進行しても自覚症状が乏しいことがあるため、症状が現れていなくても、検査による早期発見が大切です。気になる症状がある方は当院までご相談ください。
胃炎の原因と主なタイプ
急性胃炎
急性胃炎は、胃の粘膜に突然炎症が生じ、原因としてはアルコールの過剰摂取、喫煙、香辛料やカフェインなどの刺激物の摂りすぎが挙げられます。
また、胃腸の働きは自律神経によって調整されているため、精神的ストレスが加わると自律神経のバランスが崩れ、症状が悪化しやすくなります。
慢性胃炎
ピロリ菌感染
慢性的な胃炎を引き起こす要因の中で、最も一般的なものがピロリ菌感染です。この菌が長期間胃に留まると、萎縮性胃炎に進行し、胃がんのリスクが高まることがあります。
ピロリ菌は、ウレアーゼという酵素を使って胃内の尿素を分解し、強アルカリ性のアンモニアを作り出すことで、胃の強い酸性環境でも生息することができます。
この菌は、除菌治療を行って効果があった場合や、胃の機能が失われて菌が生息できなくなった場合を除いて、自然に消えることはありません。
薬剤性胃炎(NSAIDsなど)
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)などのお薬が原因で胃粘膜に炎症を引き起こすことがあります。服用回数が少なくても強い症状が出ることがあり、悪化すると胃潰瘍に進行する可能性もあります。
こうしたお薬を服用中に胃の不調が続く場合は、早めに医師へ相談し、可能であれば他のお薬への変更を検討することが望ましいでしょう。なお、NSAIDsは市販薬にも含まれているため、市販薬を使用した後に胃の不快感が現れた場合も当院までご相談下さい。
萎縮性胃炎
ピロリ菌感染などで慢性炎症が長期間続くと、胃の粘膜が委縮し、胃液や胃酸を分泌する組織が減っていきます。このような状態を萎縮性胃炎と呼びます。
さらに進行すると、胃の粘膜が腸の組織のように変化する「腸上皮化生」が起こり、一部ががん化するリスクもあります。腸上皮化生の状態では、胃内環境が大きく変化することでピロリ菌が生存できなくなり、除菌をしていないにもかかわらず検査で陰性と判定されることもあります。そのため、陰性であっても胃がんリスクが消えるわけではなく、引き続き注意が必要な状態です。
ピロリ菌感染と診断された場合は、除菌治療によって胃炎や胃がんのリスクを下げることが可能ですが、これまでの炎症によって蓄積されたダメージが完全に消えるわけではありません。除菌治療後も、定期的な胃カメラ検査で早期発見につなげましょう。
機能性ディスペプシア
胃粘膜に明確な病変が見られないにもかかわらず、胃の不調が続く「機能性ディスペプシア」は、自律神経の乱れや消化機能の低下、知覚過敏などが関与していると考えられています。
日々の生活習慣やストレスの影響を受けやすい疾患であるため、生活の見直しやストレスケアが症状の緩和に繋がります。
胃炎の検査
急性胃炎
急性胃炎が疑われる際は、問診で日常の生活習慣や食事内容を確認します。アルコールの摂取量、服用中の薬剤、直近の食事内容、カフェイン・香辛料などの刺激物の摂取状況をお聞きし、原因が特定できる場合には、それに応じた治療を進めます。
一方、原因が明確でない場合には、胃カメラ検査を実施します。検査では、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察し、炎症や潰瘍、出血などの有無や状態を確認します。必要に応じて粘膜の一部を採取し、病理検査を行うことで、より正確な診断と適切な治療へと繋げます。
慢性胃炎の場合
 慢性的な胃の不調に対しては、服用している薬剤の内容を確認しながら、症状の種類や持続期間など、これまでの経過を詳しく伺います。
慢性的な胃の不調に対しては、服用している薬剤の内容を確認しながら、症状の種類や持続期間など、これまでの経過を詳しく伺います。
その上で、必要に応じて胃カメラ検査やピロリ菌の感染有無を調べる検査を行い、胃粘膜の状態を総合的に評価します。
胃カメラ検査では、病変の有無に加えて、病変の形や範囲、表面の質感、粘膜の委縮の程度などを観察し、診断に必要な情報を収集します。
また、異常が疑われる部分から組織を採取して病理検査を行うことで、正確な診断と治療方針の決定に繋げます。
胃炎の治療
胃痛や不快感などの症状は、胃酸の分泌を抑えるお薬を中心とした治療で短期間に改善が期待できます。
ただし、自己判断で治療を中止すると再発しやすく、炎症の悪化に繋がることもあるため、医師の指示に従って治療を続けることが大切です。
ピロリ菌感染が確認された場合は除菌治療を行い、慢性炎症の改善や胃がん・胃潰瘍の予防を目指します。
お薬の副作用による胃炎では、休薬や処方の変更が最も有効ですが、変更できない場合には現在の処方を継続しつつ、消化器内科で症状を和らげる治療を行います。
また、暴飲暴食やストレスなどの生活習慣も症状の一因となるため、生活の見直しも改善に役立ちます。気になることがあればご相談ください。
薬物療法
症状や状態に応じて、胃酸の分泌を抑制するお薬に加え、胃粘膜を保護するお薬などを組み合わせながら処方を行います。
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌感染が確認された場合は、除菌治療を実施します。
除菌治療では、2種類の抗生物質と1種類の胃酸分泌抑制薬を1週間服用します。ただし、ピロリ菌は一部で抗生物質への耐性を持っており、初回の治療で除菌が成功しないこともあります。
そのため、服薬終了から一定期間後に判定検査を行い、除菌の成否を確認します。初回で除菌に失敗した場合には、抗生物質の一部を変更した上で再度治療を行い、再び判定検査を実施します。
除菌成功率は、1回目の治療でおよそ85~90%、2回目までを含めると97~98%と高い成功率が期待されます。
なお、胃カメラ検査で胃炎と診断された上でピロリ菌検査を受ける場合、保険が適用されます。また、除菌治療についても、2回目までは保険の対象です。
生活習慣の見直し
 胃炎は、日々の生活習慣とも深く関係しています。暴飲暴食、刺激の強い食事、カフェインの過剰摂取、喫煙、睡眠不足、ストレスの蓄積などは、胃の粘膜に負担をかけ、症状を悪化させる要因になります。
胃炎は、日々の生活習慣とも深く関係しています。暴飲暴食、刺激の強い食事、カフェインの過剰摂取、喫煙、睡眠不足、ストレスの蓄積などは、胃の粘膜に負担をかけ、症状を悪化させる要因になります。
無理のない範囲で構いませんので、食生活や睡眠、ストレス管理などを見直すことが、治療の効果を高めることにも繋がります。
除菌治療後も注意が必要な胃がんリスク
ピロリ菌は、井戸水や川の水などに含まれる汚染された水を介して口から体内に入り、感染するとされています。ただし、成人がこうした水を飲んでも感染することはほとんどなく、免疫力や胃酸の分泌が十分でない幼少期に感染するケースが多いと考えられています。
上下水道が整備された国では感染者は減少傾向にありますが、日本では高齢者の約8割、若年層でも約2割が感染していると推定されています。
一度感染したピロリ菌は、除菌に成功するか、あるいは炎症が進みすぎて胃の環境が菌の生存に適さなくなるまでは、胃内に留まり続けて胃粘膜を傷付けます。慢性的な炎症が続くと、やがて萎縮性胃炎へと進行し、胃がんのリスクが高まることが知られています。
除菌治療によってピロリ菌が排除されれば、炎症の改善とともに胃がんの発症リスクも低下します。ただし、過去に感染していた方は、炎症による粘膜のダメージが既に進んでいる可能性があり、感染歴のない方と比べると胃がんを発症するリスクは依然として高めです。
そのため、除菌が完了していても安心せず、定期的に胃カメラ検査を受けて早期発見・早期対応を図ることが非常に重要です。
ピロリ菌の除菌治療を受けた経験がある方は、一度ご相談ください。