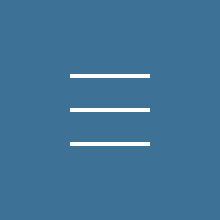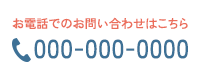足がつる・こむら返りとは
 「足がつる」という現象は、就寝中や運動中などに突発的に起こる筋肉の痙攣で、本人の意思とは関係なく数秒から数分間続くのが特徴です。特にふくらはぎに生じることが多く、この場合は「こむら返り」とも呼ばれますが、痙攣は太もも・足の裏・つま先など、足の他の部位に現れることもあります。
「足がつる」という現象は、就寝中や運動中などに突発的に起こる筋肉の痙攣で、本人の意思とは関係なく数秒から数分間続くのが特徴です。特にふくらはぎに生じることが多く、この場合は「こむら返り」とも呼ばれますが、痙攣は太もも・足の裏・つま先など、足の他の部位に現れることもあります。
足がつる(こむら返り)の原因
足がつる原因は年齢や体調によって様々です。
若年層では、運動後の筋肉疲労や脱水・ミネラル不足が引き金となり、就寝中に足がつることが多いです。また、妊娠中の方では、電解質バランスの乱れが痙攣を引き起こす原因となることがあります。
一方、中高年以降(50代以上)になると、運動不足や加齢に伴う筋肉量の減少に加え、血流の悪化も影響して足がつりやすくなります。
これらの明確な要因がない場合でも、慢性的な疲労や睡眠不足などによって足がつることがあります。
ただし、生活習慣や体調に特別な変化がないにもかかわらず、足がつる頻度が増えてきた場合には、何らかの病気が背景にある可能性も否定できません。気になる症状が続くときは、早めに当院までご相談ください。
足がつる症状を引き起こす主な疾患
下肢静脈瘤・下肢閉塞性動脈硬化症
末梢の血流が滞ることで、筋肉に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなり、足がつりやすくなります。
腎不全
人工透析を受けている方に多く見られる症状です。透析中の電解質バランスの乱れや、カルシウム・カリウム・マグネシウムの不足、カルニチン欠乏などが痙攣の要因になります。
心不全
心臓の機能低下によって血行が悪くなり、体内の水分のバランスが崩れることで筋肉が興奮しやすくなり、足をつりやすくなります。
睡眠時無呼吸症候群
慢性的な睡眠不足が続くことで、筋肉疲労が蓄積し、就寝中に足がつることがあります。
甲状腺機能異常
甲状腺ホルモンの分泌が低下すると、血流が悪化し、筋力も低下します。その結果、筋肉が過緊張を起こし、足の痙攣が生じやすくなります。
自律神経失調症・うつ病
自律神経の乱れや交感神経の過度な緊張が、筋肉の異常な収縮を引き起こし、足のつりに繋がることがあります。
神経疾患・脳腫瘍
中枢神経や末梢神経に異常があると、筋肉の制御がうまくいかなくなり、痙攣として症状が現れることがあります。
薬剤の副作用
利尿薬や不整脈の治療薬、脂質異常症に用いられる一部の薬剤には、電解質バランスに影響を与え、筋肉の痙攣を誘発するものがあります。
心不全
心臓の機能低下によって血行が悪くなり、体内の水分のバランスが崩れることで筋肉が興奮しやすくなり、足をつりやすくなります。
こむら返り・足がつることを防ぐために
水分補給
健康な方であっても、脱水や電解質の乱れがあると筋肉がつりやすくなります。特に運動や発汗が多い日は、こまめな水分補給が重要です。
なお、糖尿病がある場合はスポーツドリンクの摂取に注意が必要です。糖分が含まれているため、血糖値を上昇させ、症状を悪化させる恐れがあります。足がつったときの水分補給は、水・白湯・無糖のお茶などを選びましょう。
体を温める
体の冷えは血流を悪くし、筋肉が緊張しやすくなるため、痙攣の原因になります。日頃から冷え対策を心がけ、特に寝る前は体をしっかり温めましょう。
夏場はエアコンによる冷えが原因で就寝中に足がつることがあります。室温はやや高めに設定し、タオルケットや薄手の布団で体を冷やしすぎないように工夫すると効果的です。
湯船に浸かる
 シャワーだけで済ませるのではなく、できる限り湯船に浸かって体全体を温めましょう。血流が改善されることで筋肉の緊張が和らぎ、自律神経が整います。
シャワーだけで済ませるのではなく、できる限り湯船に浸かって体全体を温めましょう。血流が改善されることで筋肉の緊張が和らぎ、自律神経が整います。
入浴中に足を軽くマッサージするのも、こむら返りの予防に有効です。入浴後は脱水予防のために忘れずに水分を補給してください。
栄養バランスの良い食事を心がける
マグネシウム、カルシウム、カリウム、クエン酸、ビタミンB1を含む食品を意識して摂取することも大切です。以下のような食品を日常の食事に取り入れてみましょう。
- マグネシウム:わかめ、あおのり、あおさ、干しエビ、きのこ類、アーモンド、ごま
- カルシウム:小魚、海藻類、納豆、豆腐、ヨーグルト、切り干し大根、小松菜、菜の花
- クエン酸:レモンなどの柑橘類、キウイやパイナップル、梅干し
- ビタミンB1:玄米、たらこ、うなぎ、かつおぶし、大豆、ごま、豚肉
足をつる・こむら返りが頻発する場合は検査を受けましょう
足がつりやすくなる背景には、高血糖などが関係している場合があります。しかし、本人がその変化に気づかずに、スポーツドリンクを飲んで水分補給をしたり、マッサージや整体で対処しているケースも少なくありません。
もし、以前よりも足がつる頻度が増えてきたと感じたら、自己判断せずに一度医療機関を受診することをお勧めします。
糖尿病の他にも、足の痙攣には様々な要因が存在し、なかには重大な疾患が隠れていることもあります。当院では、糖尿病をはじめ、甲状腺機能異常など、足がつる原因となりうる幅広い疾患に対応しております。気になる症状があれば、お早めにご相談ください。
当院で実施する検査
まずは問診・尿検査・血液検査を行い、尿糖や血糖、甲状腺ホルモン、肝機能、腎機能などの基本的な項目を確認します。さらに必要に応じて、以下のような検査を組み合わせて実施します。
- 腹部超音波検査
- 心臓超音波検査
- 心電図検査
足がつる原因となる病気は多岐にわたるため、患者様の健康状態や生活習慣を丁寧にお伺いしながら、無理のない範囲で検査を行います。