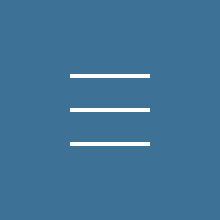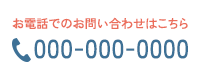このような症状でお悩みではありませんか?
 以下のような症状が見られる場合、糖尿病の可能性があります。糖尿病は血管や神経に障害を与え、動脈硬化を進めることで心筋梗塞や脳卒中のリスクを高める生活習慣病です。また、糖尿病網膜症・糖尿病腎症・糖尿病神経障害という三大合併症を引き起こし、失明や腎不全(人工透析が必要な状態)、足潰瘍や壊疽といった深刻な健康被害をもたらす恐れがあります。これらを未然に防ぐためには、できるだけ早く病気を見つけ、治療を始めることが重要です。当院では、糖尿病に特化した検査や治療を行っておりますので、症状が出ている方や健康診断で血糖値の異常を指摘された方はご相談ください。
以下のような症状が見られる場合、糖尿病の可能性があります。糖尿病は血管や神経に障害を与え、動脈硬化を進めることで心筋梗塞や脳卒中のリスクを高める生活習慣病です。また、糖尿病網膜症・糖尿病腎症・糖尿病神経障害という三大合併症を引き起こし、失明や腎不全(人工透析が必要な状態)、足潰瘍や壊疽といった深刻な健康被害をもたらす恐れがあります。これらを未然に防ぐためには、できるだけ早く病気を見つけ、治療を始めることが重要です。当院では、糖尿病に特化した検査や治療を行っておりますので、症状が出ている方や健康診断で血糖値の異常を指摘された方はご相談ください。
- 尿の量や回数が増えた
- のどの渇き、水分を多く摂るようになった
- 食事制限をしていないのに急に体重が減った
- 疲労感が続く
- 視界がぼやける
- 手足の冷えや痺れ、痛みがある
- 尿が泡立つ
- めまいや立ちくらみを起こす
- 月経不順や経血量の増加などの生理異常
- 性欲の低下 など
糖尿病とは
糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)が過剰な状態が続く病気です。通常、食事で増えたブドウ糖は、膵臓から分泌されるインスリンの働きによって細胞内に取り込まれ、血糖値が低下します。しかし、糖尿病ではインスリンの分泌が不足したり、その作用が弱まるため、血糖値が下がらず高血糖が慢性的に続きます。その結果、全身の細胞はエネルギーが不足した状態となります。
高血糖状態は血管に強い負担をかけ、動脈硬化の発症や悪化を促進し、様々な血管障害の原因となります。さらに、糖尿病になると免疫機能が弱まり、感染症にかかりやすくなるほか、ケガや傷の治りも遅くなる傾向があります。
あけぼの橋内科・内視鏡内科の糖尿病診療
 令和1(2019)年の「国民健康・栄養調査」によれば、「糖尿病が強く疑われる」とされる人は、男性で19.7%、女性で10.8%に上ると報告されています。治療を受けずに高血糖の状態が続くと、腎臓・眼・神経などに重い合併症を引き起こし、動脈硬化が進んで心筋梗塞や脳卒中の危険性も高まります。さらに、免疫力が弱まることで感染症にかかりやすくなり、重症化やケガの治りの遅れといった影響も生じます。
令和1(2019)年の「国民健康・栄養調査」によれば、「糖尿病が強く疑われる」とされる人は、男性で19.7%、女性で10.8%に上ると報告されています。治療を受けずに高血糖の状態が続くと、腎臓・眼・神経などに重い合併症を引き起こし、動脈硬化が進んで心筋梗塞や脳卒中の危険性も高まります。さらに、免疫力が弱まることで感染症にかかりやすくなり、重症化やケガの治りの遅れといった影響も生じます。
糖尿病には、自己免疫の異常で発症する1型糖尿病と、遺伝的素因に生活習慣の影響が加わって起こる2型糖尿病があります。日本では全体の約95%が2型糖尿病で、このタイプは進行するまで自覚症状が乏しく、治療の開始が遅れて合併症に至る例も少なくありません。
当院では、患者様1人ひとりの病状や生活習慣を考慮し、相談しながら無理のない治療方針を決定しています。生活改善の指導も、できる限りストレスを抑えつつ効果が得られる方法をご提案します。糖尿病の管理と合併症予防のため、丁寧にサポートを行っていますので、安心してご相談ください。
糖尿病の種類
1型糖尿病
ウイルス感染などをきっかけとして自己免疫の異常が起こり、膵臓のランゲルハンス島β細胞が壊されてインスリンが分泌されなくなる病気です。2型が加齢とともに増加するのに対し、1型は小児や若年層にも多く見られます。インスリンは、食後に増えた血糖を細胞内へ取り込み、血糖値を下げる働きを担います。不足すると高血糖が続き、血管を傷つけるだけでなく、細胞がエネルギーを利用できなくなります。ほとんどのケースで、不足分を補うためのインスリン注射が必要です。
2型糖尿病
糖尿病の大部分を占めるタイプで、遺伝的要因に加え、過食・運動不足・ストレスなどが引き金となり、インスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性)状態が起こります。さらに、膵臓からのインスリン分泌も減少することがあります。加齢とともに発症リスクは高まりますが、近年は若年層での発症も増加しています。日本人は元々インスリン分泌量が少ない傾向があり、肥満でなくても発症することがありますので、注意が必要です。
2型糖尿病の治療
糖尿病は完治が難しいものの、専門医による治療を受けて血糖を正常範囲に維持することで、合併症や動脈硬化の進行を抑えることが可能です。早期発見・早期治療により、発症前と変わらない生活を維持できる可能性が高まります。生活習慣の改善は治療の基本で、食事療法や運動療法は必須です。薬物療法やインスリン療法を併用する場合でも、生活習慣の見直しは効果を高めます。また、高血圧や脂質異常症といった併発しやすい病気の予防にも効果的です。
妊娠糖尿病
 妊娠中に初めて糖代謝異常が発見された場合を指し、妊婦の約7〜9%に発症します。血糖管理が不十分だと、母体や胎児に影響が出る恐れがあります。なお、妊娠前に糖尿病と診断されていた場合や、妊娠中に明確な糖尿病と診断された場合は、妊娠糖尿病には該当しません。
妊娠中に初めて糖代謝異常が発見された場合を指し、妊婦の約7〜9%に発症します。血糖管理が不十分だと、母体や胎児に影響が出る恐れがあります。なお、妊娠前に糖尿病と診断されていた場合や、妊娠中に明確な糖尿病と診断された場合は、妊娠糖尿病には該当しません。
その他の糖尿病
遺伝子異常や他の病気によって発症するケースもあります。遺伝子異常では、インスリン分泌に関与するβ細胞の機能や、インスリン作用の伝達に関わる遺伝子に異常が生じます。また、甲状腺・副腎・下垂体などの内分泌疾患、肝疾患、膵外分泌疾患、感染症などが原因となる場合もあります。さらに、薬の副作用が原因となることもあり、この場合は原因となる病気の治療やお薬の変更が必要です。
糖尿病の三大合併症
糖尿病は発症初期に自覚症状がほとんどなく、血液検査や尿検査などの健診で発見されることが多い病気です。血糖値の異常を指摘された場合は、症状がなくても早めに受診することが大切です。高血糖のまま放置すると、全身の血管に障害が生じ、動脈硬化の進行による心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。特に「糖尿病三大合併症」と呼ばれる障害は重症化すると失明や腎不全、足潰瘍・壊疽といった深刻な状態を招くため、早期発見と継続的な治療が欠かせません。
糖尿病神経障害
高血糖が神経にダメージを与えることで起こる合併症で、三大合併症の中でも比較的早い段階で症状が出やすいのが特徴です。手足の痺れや灼けるような痛み、冷え、ケガやヤケドの痛みを感じにくくなるといった知覚障害が代表的です。さらに、自律神経が障害されると筋力低下や消化器症状、発汗異常、立ちくらみなどが現れることもあります。進行すると足潰瘍や壊疽が生じ、切断が必要になる場合もあります。
糖尿病網膜症
網膜は、物を見るために必要な光の情報を受け取る組織で、多くの毛細血管が張り巡らされています。糖尿病網膜症は、高血糖によってこれらの血管が損傷し、眼底出血や浮腫を引き起こす病気です。視力の大幅な低下や失明に至る危険があるものの、初期は自覚症状が乏しいため、早期発見には定期的な眼科検診が不可欠です。日本では中途失明原因の第2位で、白内障を伴うこともあります。
糖尿病腎症
慢性的な高血糖が腎臓に負担をかけ続けることで、腎機能が少しずつ低下していきます。進行すると尿の生成や老廃物の排出がうまくできなくなり、腎不全へと移行します。人工透析が必要になる原因は様々ありますが、糖尿病腎症が最大の原因です。糖尿病と診断された場合は、尿検査や血液検査を定期的に受け、尿蛋白や腎機能を評価することが大切です。
その他の合併症
糖尿病は三大合併症以外にも、脳梗塞や脳卒中、心筋梗塞、感染症、皮膚疾患、下肢閉塞性動脈硬化症、歯周病など、多岐にわたる病気の発症や悪化リスクを高めます。
糖尿病の検査
糖尿病の診断や経過観察には、採血による血糖値とHbA1cの測定が欠かせません。発症初期は自覚症状がほとんどないため、健診などで高血糖を指摘された場合は、症状がなくても早めの受診が重要です。また、治療を始めた後も定期的に検査を行い、血糖を確認することが合併症予防に繋がります。
血糖値
血液中に含まれるブドウ糖の量を測定する検査です。糖尿病では、食前や食後、またはその両方で血糖が高くなる場合があります。特に食後に急激かつ大きな血糖上昇を示すタイプは、心疾患や脳卒中に繋がる可能性が高いと言われています。そのため、空腹時だけでなく食後の血糖値も測定し、適切な管理に役立てることが大切です。
HbA1c(ヘモグロビン・エー・ワンシー)
HbA1cとは、赤血球内のヘモグロビンとブドウ糖が結合した割合を表す値です。この数値から、過去1〜2ヶ月間の平均血糖値を推測できます。空腹時や食後の血糖値が一時的な状態を示すのに対し、HbA1cは高血糖がどれだけの期間続いたかを反映するため、糖尿病の早期診断や治療効果の判定、合併症リスク評価に欠かせません。一般的に6.5%以上で受診が推奨され、5.6%以上は糖尿病予備群として経過観察が望まれます。
糖尿病の治療
治療の基本は食事療法と運動療法で、これらだけでは血糖コントロールが難しい場合に薬物療法を加えます。食事では、栄養バランスや摂取量、食べる順番を工夫することで血糖値の安定を図ります。運動は、少し汗ばむくらいの軽い有酸素運動を1日30分以上、継続して行うことが推奨されます。これにより糖の消費が促され、筋力が向上し、血流や代謝が改善されることでインスリン作用の向上も期待できます。
薬物療法では、患者様の状態に合わせて経口薬の処方やインスリン注射を行い、血糖管理をサポートします。