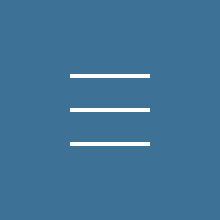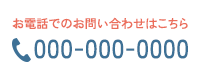下痢とは
下痢とは、水分を多く含んだ柔らかい便が排出される状態を指し、便の形状や含有する水分の量によって分類されます。
便の形状による分類
健康的な便は、バナナのような形状をしており、適度な硬さと水分を保っています。これに対して、水分が多く緩んだペースト状の便は「軟便」、液体状になったものは「下痢便」とされます。
水分量による分類
大腸で水分の吸収が行われ、便の硬さはその吸収の程度によって左右されます。正常な便の水分含有量は70~80%程度とされていますが、これが80~90%程度になると軟便、それ以上になると下痢便とされます。
持続期間による分類
比較的短期間で治まるものは「急性下痢」、具体的には数時間から2週間以内のものを指します。一方で、3〜4週間以上症状が続く場合は「慢性下痢」とされます。
下痢で受診すべきタイミング
救急対応が求められるケース
- 1時間に複数回の排便がある(非常に頻回な下痢)
- 下痢に加え、大量の血が混じった便が出る
- 激しい腹痛や38℃以上の高熱を伴っている
- 吐き気や嘔吐があり、水分摂取ができない状態
消化器内科の診察が必要なケース
- 1時間ごとに下痢が続いている
- 慢性的に下痢が続いている
- 便秘と下痢を交互に繰り返す
- 腹痛や吐き気、軽度の嘔吐などがある
- 血液や粘液を含んだ便、または黒色のタール便が出る
下痢の主な原因

下痢は、以下のような様々な要因によって引き起こされます。
- 暴飲暴食
- 香辛料など刺激の強い食べ物の過剰摂取
- 精神的ストレス
- 細菌やウイルスによる感染症
- お薬の副作用
- クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患
など
これらの要因によって腸の運動が活発になり、便が大腸内を通常よりも早く通過してしまうと、本来吸収されるべき水分が十分に吸収されず、結果として水分を多く含んだ便(下痢)が排出されるようになります。
下痢の症状
下痢は、急な腹痛とともに強い便意を伴い、水のような便や泥状の便が1日に何度も出るのが特徴です。お腹がゴロゴロと鳴る程度の軽い違和感のみが現れるケースもあります。便の状態は、原因を推定するうえで重要な手がかりとなるため、診察時には便の形状や色などの詳細をお伝えください。
また、吐き気・嘔吐・発熱・倦怠感などが続き、脱水のリスクが高まっている場合には、早めに医療機関を受診することが必要です。特に、血液や粘液を含んだ便、鮮血が混ざる下痢が見られる際は、大腸の炎症や潰瘍性病変が疑われますので、迅速な対応が求められます。
急性下痢の場合
急性下痢の多くは、細菌やウイルスによる感染が原因となる急性腸炎です。突然激しい症状が現れた場合には、食中毒、暴飲暴食、冷たいものの摂取、または感染以外の腸炎などが考えられます。
感染性の下痢を引き起こす主なウイルスには、ロタウイルスやノロウイルスがあり、細菌では病原性大腸菌(O-157など)、サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオなどが代表的です。
慢性下痢の場合
下痢が3〜4週間以上持続する状態を指します。原因としては、以下のようなものが挙げられます。
- 潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患
- 大腸がんなどの器質的疾患
- 自律神経の乱れによる腸の運動異常(過敏性腸症候群)
- 精神的ストレス
- 手術後の影響やお薬の副作用
下痢の原因となる主な消化器疾患
食中毒・感染性腸炎
ノロウイルスやロタウイルスをはじめ、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ、病原性大腸菌(O-157など)、黄色ブドウ球菌などの感染によって急性下痢が起こることがあります。これらは主に飲食物を介して感染し、激しい下痢に加えて、嘔吐や発熱を伴うケースも多いです。
過敏性腸症候群
器質的異常が見られないにもかかわらず、便秘と下痢を交互に繰り返すのが特徴の疾患です。自律神経の乱れや腸の蠕動運動の調節異常が関与しており、「下痢型」「便秘型」「混合型(下痢と便秘の両方を繰り返す)」「分類不能型」に分けられます。
潰瘍性大腸炎
大腸の粘膜に慢性的な炎症が生じる病気で、主な症状は下痢・血便・腹痛です。原因は明確に解明されておらず、現在も根本的な治療法が確立されていないことから、難病に指定されています。症状が激しく現れる「活動期」と、症状が落ち着く「寛解期」を繰り返す経過が特徴です。
大腸がん・大腸ポリープ
どちらも早期には自覚症状が乏しいため、気づかれにくいのが特徴です。しかし、進行することで腸内が狭くなり、便の通過時に粘膜が傷つくことで出血を引き起こすことがあります。その結果、血便として症状が現れる場合があります。
下痢の診断・検査
下痢の原因を正確に把握するため、まずは便の形状や色、発症時期、発症の頻度、普段の生活習慣などを丁寧にお伺いします。そのうえで、必要に応じて各種検査を行い、原因を特定します。
急性下痢の場合
食中毒が疑われる場合は、ウイルスや細菌など感染源の特定が優先となります。血液検査や検便によって、原因となる病原体の有無を調べて診断します。
慢性下痢の場合
 慢性的に下痢が続いている場合には、より詳細な問診を行ったうえで、血液検査や大腸カメラ検査を行います。大腸カメラでは、大腸内の粘膜を直接観察できるため、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患、さらには大腸がんの早期発見・確定診断が可能です。
慢性的に下痢が続いている場合には、より詳細な問診を行ったうえで、血液検査や大腸カメラ検査を行います。大腸カメラでは、大腸内の粘膜を直接観察できるため、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患、さらには大腸がんの早期発見・確定診断が可能です。
これらの疾患は、近年日本国内でも患者数が増加傾向にあり、早期の診断と治療が非常に重要です。便の異常や気になる症状が続く場合には、お早めにご相談ください。
下痢の治療
下痢が続いている場合は、脱水症状を防ぐために十分な水分補給を行うことが大切です。治療は症状の性質に応じて異なり、急性・慢性により対処法が変わります。
急性下痢の場合
水分摂取を積極的に行い、脱水が懸念される場合には点滴での補水を検討します。
食事は無理のない範囲で消化にやさしいものを少量ずつ取り入れ、腸への負担を抑えます。必要に応じて、整腸剤や抗菌薬などを使用した薬物療法を行います。
なお、市販の下痢止め薬の使用には注意が必要です。感染症が原因で下痢が起きている場合、排便によって体外に排出されるはずの病原体が体内に留まることで、悪化する可能性もあります。薬の使用は、医師の指示に従って行いましょう。
慢性下痢の場合
慢性下痢の背景には、消化器疾患やお薬の副作用、生活習慣の影響などが隠れていることが多いため、まずは原因の特定が治療の第一歩となります。
食事面では、脂っこい料理や刺激の強い食材、アルコールなどは避ける必要があります。胃腸への負担が少ない、柔らかく消化しやすい食事を心がけましょう。例えば、白がゆ・うどん・バナナ・すりおろしたリンゴなどが適しています。
また、服用中のお薬によって下痢が起きている場合には、医師と相談しながら薬剤の変更や量の調整を行うことも検討されます。
下痢でお悩みの方は当院までご相談ください
 下痢は一時的な不調に留まらず、消化器の疾患や他の病気のサインである場合もあります。原因を明確にすることで、適切な治療に繋がり、生活の質(QOL)も大きく改善されます。
下痢は一時的な不調に留まらず、消化器の疾患や他の病気のサインである場合もあります。原因を明確にすることで、適切な治療に繋がり、生活の質(QOL)も大きく改善されます。
当院では、消化器内科の専門医が丁寧な診察と検査を通じて、下痢の根本的な原因を見極め、症状の緩和を目指した治療を行っています。慢性的な下痢や繰り返す症状でお困りの方は、一度当院へご相談ください。