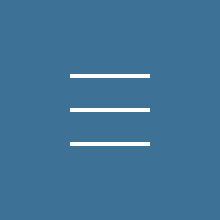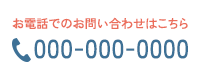機能性ディスペプシアとは
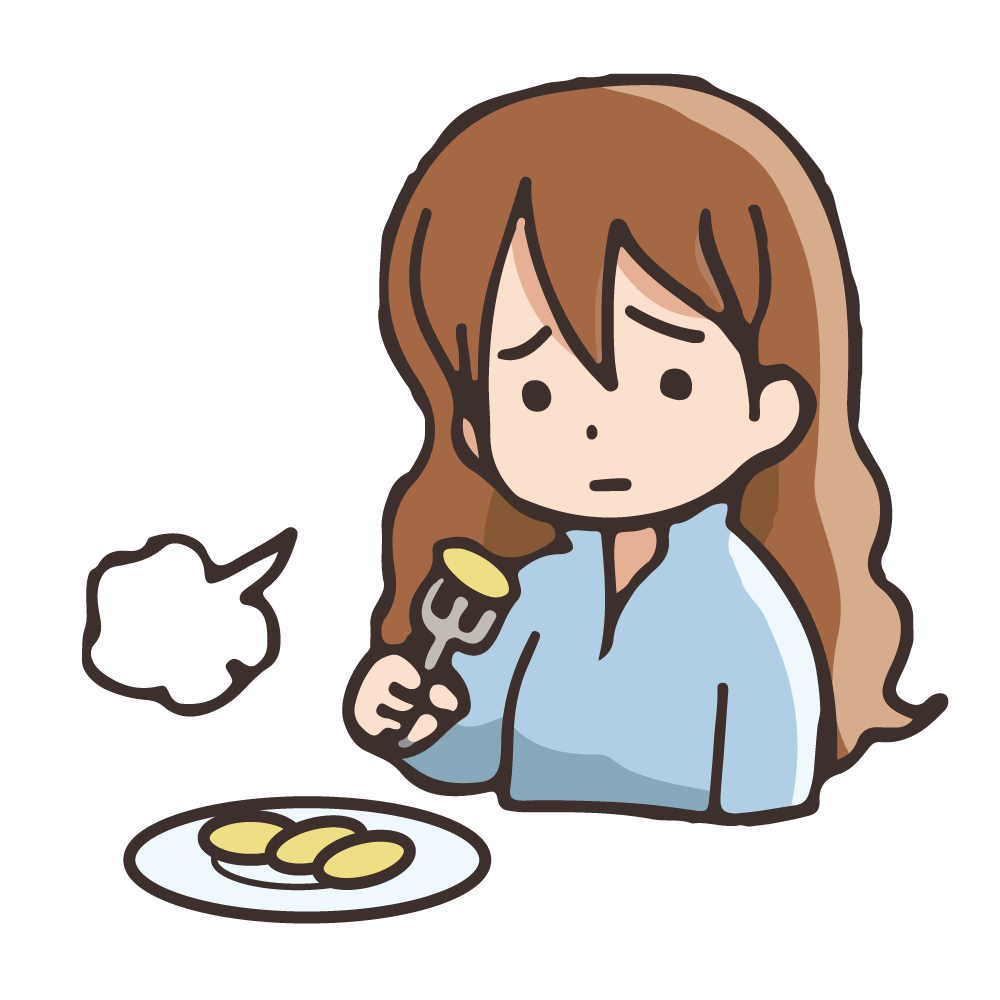 機能性ディスペプシアは、みぞおちの違和感、胸焼け、胃もたれ、すぐに満腹になるといった消化器の不調が現れる病気です。FD(Functional Dyspepsia)とも呼ばれますが、胃カメラ検査などで明らかな異常が見つからないのが特徴です。そのため、かつては「神経性胃炎」や「自律神経の乱れ」と診断されることが多く、適切な治療を受けられないまま長年悩まれてきた方も少なくありません。
機能性ディスペプシアは、みぞおちの違和感、胸焼け、胃もたれ、すぐに満腹になるといった消化器の不調が現れる病気です。FD(Functional Dyspepsia)とも呼ばれますが、胃カメラ検査などで明らかな異常が見つからないのが特徴です。そのため、かつては「神経性胃炎」や「自律神経の乱れ」と診断されることが多く、適切な治療を受けられないまま長年悩まれてきた方も少なくありません。
現在では、胃腸の運動機能低下や、消化管が刺激に敏感になる「知覚過敏」が主な原因とされ、消化器内科における治療が有効であると考えられています。症状を引き起こす要因としては、消化管の蠕動運動の異常(亢進・低下)、胃の拡張が不十分な「適応性弛緩障害」、胃酸分泌の変化、生活習慣、ストレスや環境因子など多岐にわたります。
こうした様々な原因に応じて、治療方法も異なります。当院では、消化器内科の専門知識と経験をもつ医師が、患者様1人ひとりの症状や生活背景を丁寧に確認し、最も適した治療へと導いています。
長引く胃の不快感や食欲不振がある方は、お早めにご相談ください。
機能性ディスペプシアの主な症状
以下のような不快な症状が数ヶ月以上に継続するのが特徴です。
- 胃の不快感
- 少しの食事で満腹になる(早期満腹感)
- 胸焼けや吐き気
- みぞおち周辺の不快感
- げっぷが増える
- 胃の圧迫感
- 食欲がわかない
- 吐き気・嘔吐
機能性ディスペプシアの原因
複数の因子が複雑に関与して症状が現れると考えられています。なかでも、精神的ストレスや自律神経の乱れ、胃腸の運動機能低下、胃の知覚過敏などが影響すると考えられています。
ストレスの影響
強いストレスや緊張状態が続くと、自律神経のバランスが崩れ、消化器の働きにも支障をきたします。結果として、消化管の運動機能に乱れが生じ、機能性ディスペプシアの発症に繋がるとされています。
消化管の運動異常
胃や腸では、食べたものを先へ送る「蠕動運動」が起こっていますが、この働きが鈍くなると、食物が胃に長く留まり、胃もたれや早く満腹になる感じ、吐き気などが起こりやすくなります。
知覚過敏
胃や食道の粘膜が過敏になることで、通常であれば気にならない刺激にも強く反応し、違和感や痛みを覚えやすくなります。これにより、胃の不快感や胸焼け、早期満腹感などの症状が現れます。
機能性ディスペプシアの診断
 機能性ディスペプシアは、胃炎・胃潰瘍・逆流性食道炎・胃がんなどの病気と症状が似ているため、慎重な診断が必要です。国際的な診断基準である「RomeⅢ分類(2006年)」をもとに、患者様の症状を詳しく伺い診断を行います。
機能性ディスペプシアは、胃炎・胃潰瘍・逆流性食道炎・胃がんなどの病気と症状が似ているため、慎重な診断が必要です。国際的な診断基準である「RomeⅢ分類(2006年)」をもとに、患者様の症状を詳しく伺い診断を行います。
そのうえで、胃カメラ検査により、潰瘍や腫瘍、炎症などの器質的疾患が存在しないことを確認することで、最終的に機能性ディスペプシアと診断されます。
当院では、鼻から挿入する経鼻内視鏡や、鎮静剤を使って眠っているような状態で受けられる胃カメラ検査も行っており、苦痛を抑えた検査が可能です。検査に不安のある方も、どうぞお気軽にご相談ください。
機能性ディスペプシアの治療
当院では、患者様の症状や生活背景に応じて、お薬による治療に加え、食事や生活リズムの見直しも含めた総合的なアプローチを行っています。
薬物療法
症状や体質、生活習慣などを丁寧に確認した上で、胃酸の分泌を抑えるお薬や、消化管の動きを整えるお薬を処方します。また、漢方薬を組み合わせることで、より幅広い症状に対応しています。
再診時には、前回の治療経過やお悩みをしっかりとお聞きし、必要があればお薬の種類や量を調整します。ストレスの影響が大きいと判断される場合には、抗うつ薬などの処方が有効なこともあります。
生活習慣・食習慣の見直し
毎日の就寝・起床時間を一定に保つことで自律神経の乱れが整いやすくなります。特に朝日を浴びることは体内時計のリセットに効果があり、生活のリズムを取り戻すうえで有効です。
食事は1日3食をできるだけ決まった時間に摂るよう心がけ、栄養バランスの取れた食事をしっかり噛んで食べることが基本です。消化機能が弱っているときには、脂っこいものや刺激物を避け、胃にやさしいメニューを選ぶようにしましょう。
また、食後すぐの激しい運動や就寝は、胃の負担になるため控えてください。