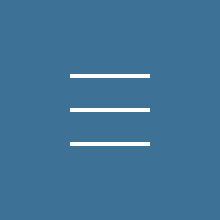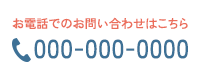おならのお悩みはお気軽にご相談ください
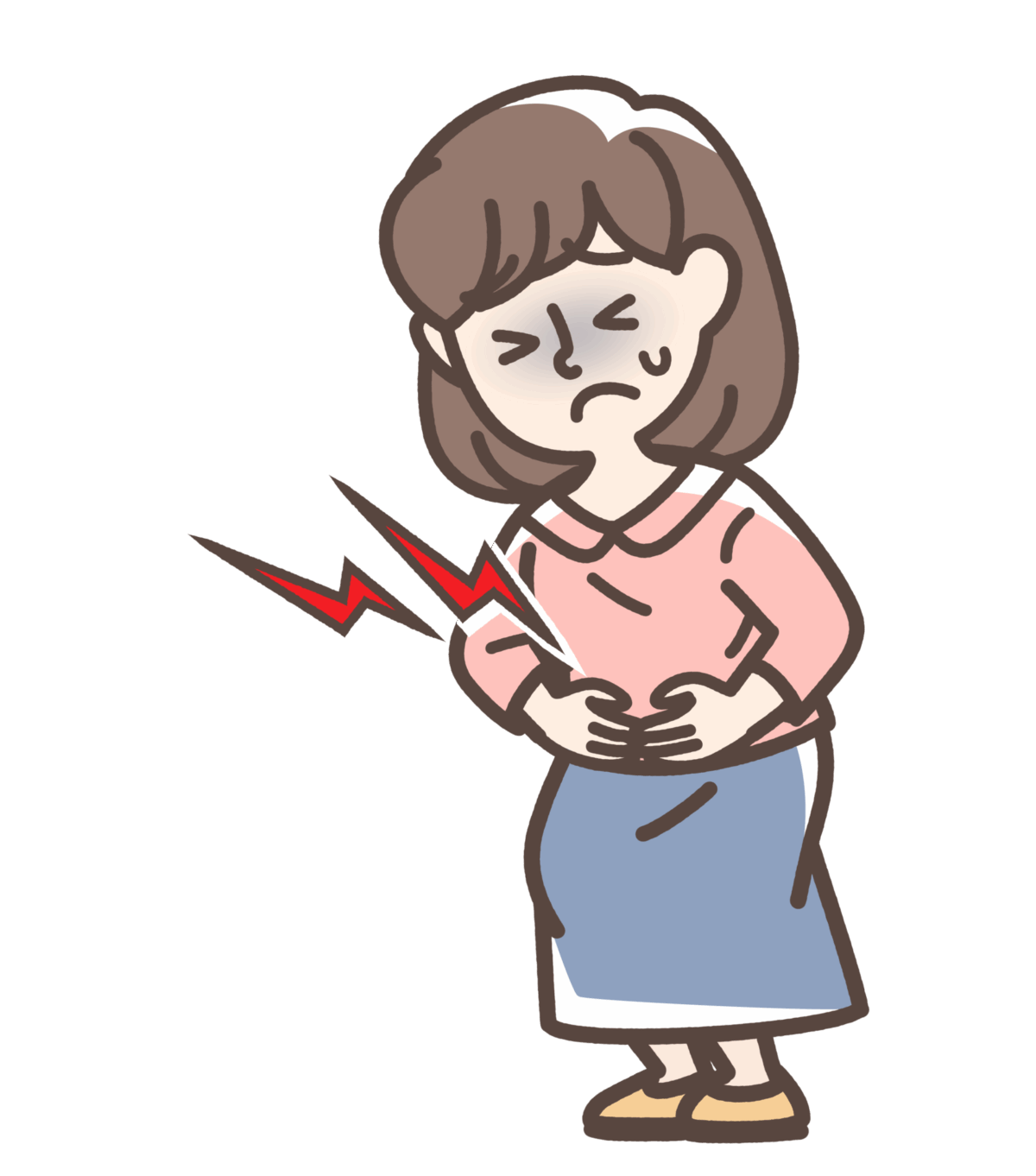 おならとは、腸内に溜まったガスが肛門から体外へ排出される生理的な現象です。発生するガスは、食事や会話中に無意識に飲み込んだ空気、腸内細菌が食べ物を分解する際に発生する成分が混ざり合ったものです。
おならとは、腸内に溜まったガスが肛門から体外へ排出される生理的な現象です。発生するガスは、食事や会話中に無意識に飲み込んだ空気、腸内細菌が食べ物を分解する際に発生する成分が混ざり合ったものです。
日常的に誰にでも起こるものですが、緊張時や食生活の乱れ、消化器系の不調があると、おならの頻度が増えたり、においが気になったりすることがあります。
おならの症状でお悩みの方は、当院までお気軽にご相談ください。
おならの回数が増える主な原因
食物繊維の多い食事
 食物繊維は腸内環境を整える上で重要な栄養素で、便通の改善にも効果的です。しかし、摂取量が多すぎると腸内で発酵が活発になり、ガスの発生量が増えておならの回数も多くなります。このタイプのガスは、通常ほとんどにおいを伴いません。
食物繊維は腸内環境を整える上で重要な栄養素で、便通の改善にも効果的です。しかし、摂取量が多すぎると腸内で発酵が活発になり、ガスの発生量が増えておならの回数も多くなります。このタイプのガスは、通常ほとんどにおいを伴いません。
肉類の過剰摂取
肉類に多く含まれるタンパク質は、消化しきれずに大腸まで達すると、腸内の悪玉菌(例:ウェルシュ菌)によって分解されます。その過程で、アンモニア・スカトール・硫化水素・二酸化硫黄といった強い悪臭を放つガスが生成され、においの強いおならの原因となります。
便秘
便秘が続くと、腸内にガスや老廃物が長時間留まることで、発酵でにおいが強くなる傾向があります。また、腸管内のガスが吸収されて血液中に取り込まれた場合、それが肺を経由して呼気に移ることもあり、口臭が気になることもあります。
便秘はこちら
ストレスや緊張
ストレスや緊張により無意識に空気を飲み込む呑気症を引き起こすことがあります。これにより胃腸にガスが溜まりやすくなり、結果的におならの頻度が増加します。
消化器系の疾患
過敏性腸症候群や呑気症などの機能性消化管疾患は、腸内ガスの蓄積を招きやすく、おならが増える原因となります。また、大腸がんが進行すると腸の動きが妨げられ、便秘を引き起こし、それに伴ってガスの排出量も増加する場合があります。
おならの原因となる主な疾患
呑気症
呑気症とは、食事や会話中などに無意識に多量の空気を飲み込んでしまい、その一部がげっぷやしゃっくりとして排出されず腸内に溜まることで起こります。腸に蓄積した空気が排出されることで、おならの回数が増加します。
早食いや一気飲み、口呼吸の癖がある方、神経質な方、ストレスを溜め込みやすい方などに多く見られる傾向があります。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群は、腸に明確な異常が認められないにもかかわらず、慢性的に下痢・便秘・腹痛といった症状が繰り返される疾患です。ストレスや疲労、気温の変化が引き金となることが多く、ガスが溜まりやすくなるため、おならの増加にも繋がります。
おならの悩みは他人には打ち明けづらく、気にしすぎてさらに便秘が悪化したり、人前に出ることが不安になったりと、日常生活にも影響が及ぶことがあります。
大腸がん
初期の大腸がんは症状が出にくいため、気づかないうちに進行していることがあります。進行すると、腹部の張りや便秘・下痢、便の形状が細くなる、血便・下血などの症状が現れます。腫瘍によって腸の内腔が狭くなると、ガスや便が通過しにくくなり、おならの頻度やにおいにも影響を及ぼすことがあります。
なお、便潜血検査で異常が出なかった場合でも、直腸から離れた部位にがんが潜んでいる可能性は否定できません。大腸がんは早期発見が鍵となるため、定期的に大腸カメラ検査を受けましょう。
おならが出なくなる疾患
腸閉塞(イレウス)
腸管の癒着や狭窄、腸の蠕動運動が低下したりすることで、便やガスが腸内に滞ってしまう状態です。
腹部の張りや激しい腹痛、吐き気、嘔吐、膨満感といった症状が現れ、進行すると便もおならも全く出なくなります。これにより初めて異常に気づくケースもあります。
放置すると腸の壊死や命に関わる重篤な合併症を引き起こすこともあるため、早期の対応が必要です。お腹の張りが続いているのにガスが出ないという場合には、すぐに当院までご相談ください。
大腸がん・大腸ポリープ
進行した大腸がんや大きな大腸ポリープが腸管内を狭くすると、便やガスの通過が妨げられ、おならが出にくくなることがあります。
このような状態は、腸閉塞と同様に速やかな医療介入が必要です。ガスや便の出にくさに気づいた段階で速やかに当院までご相談ください。
日常生活で取り組める予防法
肉類の摂り過ぎに注意する
動物性タンパク質を過剰に摂取すると、大腸で悪玉菌によって分解される際にアンモニアや硫化水素などのにおいの強いガスが発生します。その結果、おならのにおいが強くなることがあります。このような状態を防ぐために、腸内の善玉菌を増やすことが重要です。ヨーグルトや発酵食品など、善玉菌を豊富に含む食品を日常的に取り入れましょう。
生活習慣を見直す
便秘は腸内にガスや便が滞る原因となり、膨満感やおならの増加に繋がります。次のような生活習慣を意識することで、腸の働きをサポートできます。
- おならを我慢しない
- 便意を我慢しない
- ウォーキングや軽い運動を日課にする
- 食物繊維を積極的に摂る
- 水分をこまめに摂取する
また、ヨーグルトや乳酸菌飲料などの発酵食品も腸内環境の改善に役立ちます。便意を我慢しないことや、毎日の食事と運動を見直すことが大切です。
ストレスをコントロールする
ストレスは胃腸の働きに大きく影響します。特に、過敏性腸症候群などは心理的ストレスによって症状が悪化することが知られています。
不安や緊張が強い方は、おならのにおいや腹部の張りが気になりすぎてしまい、さらに悪化するという悪循環に陥ることもあります。
日常的にリラックスする時間を持ち、旅行や趣味、運動など、自分に合った方法でストレスを発散することも大切です。
おならの対策
おならが気になるときは専門医にご相談ください
 おならの回数が極端に多くなる、強いにおいや下痢、腹痛などを伴う場合には、消化器系の疾患が背景にある可能性もあります。
おならの回数が極端に多くなる、強いにおいや下痢、腹痛などを伴う場合には、消化器系の疾患が背景にある可能性もあります。
こうした悩みは人に相談しにくく、気にしすぎることでかえって便秘や腹部の不快感を悪化させてしまうことも少なくありません。
当院では、消化器症状に精通した医師が丁寧に向き合い、原因を明らかにしたうえで適切な対応を行っています。どうぞお気軽にご相談ください。