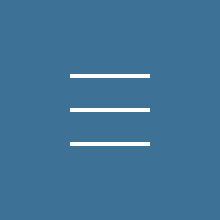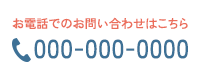- 妊娠糖尿病とは
- 妊娠糖尿病で引き起こされる疾患
- 妊娠糖尿病になりやすい体質
- 妊娠糖尿病の予防と早期発見のために
- 妊娠糖尿病の治療
- 妊娠糖尿病における低血糖への注意
- 出産後も油断せず、継続的な健康管理を
妊娠糖尿病とは
 妊娠中に初めて血糖値の異常が認められた状態を「妊娠糖尿病」と呼びます。これは、元々糖尿病を患っていた方が妊娠する「糖尿病合併妊娠」とは区別されます。多くの場合、出産後に血糖値は自然に安定しますが、母体や胎児に悪影響を及ぼすこともあるため、早期の発見と治療が欠かせません。
妊娠中に初めて血糖値の異常が認められた状態を「妊娠糖尿病」と呼びます。これは、元々糖尿病を患っていた方が妊娠する「糖尿病合併妊娠」とは区別されます。多くの場合、出産後に血糖値は自然に安定しますが、母体や胎児に悪影響を及ぼすこともあるため、早期の発見と治療が欠かせません。
妊娠糖尿病の発症頻度
妊娠糖尿病は珍しい病気ではなく、全妊婦のうち約12%に見られるとされており、妊娠中に比較的よく起こる代謝異常の1つです。
妊娠糖尿病の原因
健康な状態では、食後に上昇した血糖値は膵臓から分泌されるインスリンによってコントロールされます。しかし、妊娠中は胎盤の発達により、インスリンの効き目が弱くなる「インスリン抵抗性」が強まり、膵臓はこれに対抗するために多量のインスリンを分泌します。
このような状態が続くと、血糖値は正常より高くなるものの、糖尿病の診断基準には達しない中間的な数値となり、これを「妊娠糖尿病」と定義します。妊娠後期には特にインスリン抵抗性が増し、血糖管理が難しくなる傾向がありますが、出産後に胎盤が体外へ排出されることでインスリンの効きも回復し、血糖値は少しずつ正常範囲に戻ります。
妊娠糖尿病の症状
妊娠糖尿病はほとんどの場合、自覚症状が現れません。そのため、定期的な妊婦健診による早期発見が重要です。母体や赤ちゃんへの影響を未然に防ぐためにも、健診スケジュールを守って受診しましょう。
妊娠糖尿病の診断
妊婦健診の際、尿検査で尿糖が検出された場合には、さらに詳しい検査として空腹時血糖値や「75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)」が行われます。これらの検査結果に基づき、妊娠糖尿病と診断されることがあります。
診断がついた際には、産婦人科医が糖尿病専門医を紹介し、連携して治療を進めていきます。
診断基準(空腹時血糖値検査とOGTT)
以下のいずれかの基準を満たす場合、妊娠糖尿病と確定診断されます。
- 空腹時血糖値が92mg/dL以上
- 75g経口ブドウ糖負荷試験において
1時間後の血糖値が180mg/dL以上
2時間後の血糖値が153mg/dL以上
なお、これらの数値を大きく上回る場合は「妊娠糖尿病」ではなく、「妊娠中に判明した明らかな糖尿病」と診断されます。
妊娠糖尿病で引き起こされる疾患
妊娠糖尿病は自覚症状に乏しいにもかかわらず、母体や胎児に深刻な健康被害をもたらすことがあります。以下に、母体と赤ちゃんそれぞれに生じうる代表的な合併症をまとめます。
母体に生じる可能性のある合併症
妊娠糖尿病を発症すると、以下のような症状や疾患が生じるリスクが高まります。
- 流産・早産
- 羊水過多
- 血管障害
- 網膜症
- 妊娠高血圧症候群
- 膀胱炎・腎盂炎
- ケトアシドーシス(重篤な代謝異常で、脱水、意識障害、昏睡、ショック状態を引き起こすことがあります)
胎児・新生児に生じる可能性のある疾患
母体の血糖コントロールが不十分な場合、赤ちゃんにも以下のような健康リスクが及ぶ可能性があります。
- 子宮内胎児死亡
- 新生児低血糖
- 低カルシウム血症
- 新生児ビリルビン血症
- 先天奇形
- 発育の遅れ
- 呼吸窮迫症候群
- 電解質異常
- 多血症
- 心肥大
- 黄疸
また、妊娠中に高血糖の状態が続くと、赤ちゃんが過剰な栄養で「巨大児」となるリスクがあり、分娩時に肩甲難産が発生しやすくなります。その結果、帝王切開での出産が必要になるケースもあります。
さらに、妊娠糖尿病による高血糖状態が続いた場合、出生後の赤ちゃんは肥満傾向になりやすく、メタボリックシンドロームのリスクが高くなることが報告されています。このため、将来的な生活習慣病や動脈硬化などの発症リスクが懸念されています。
妊娠糖尿病になりやすい体質
妊娠糖尿病はどの妊婦にも発症する可能性がありますが、特に注意が必要とされる体質や背景がいくつか知られています。以下の項目に該当する方は、発症リスクが高いため、予防や早期の検査・対応が重要です。
- 35歳以上
- 妊娠中の急激な体重増加
- 妊娠前のBMIが25以上の肥満体型
- 両親や祖父母など、近親者に糖尿病の既往がある
- 原因が特定できない早産・流産・死産を経験している
- 先天性疾患を持つお子様を出産したことがある
- 現在、妊娠高血圧症候群の診断を受けている
- 過去に妊娠高血圧症候群を発症したことがある
など
妊娠糖尿病の予防と早期発見のために
妊娠糖尿病は、日々の生活習慣を見直すことで予防が可能なケースも多く、妊婦健診による早期発見が重要です。
バランスの取れた食生活を意識する
 妊娠中に体重が過度に増加すると、体内の脂肪細胞がインスリンの働きを妨げることで、妊娠糖尿病を引き起こす原因となることがあります。そのため、食事の量を適切に調整し、栄養バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。
妊娠中に体重が過度に増加すると、体内の脂肪細胞がインスリンの働きを妨げることで、妊娠糖尿病を引き起こす原因となることがあります。そのため、食事の量を適切に調整し、栄養バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。
妊娠中の適正なエネルギー摂取量
エネルギー量の目安は以下の計算式で求められます。
標準体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22
必要なエネルギー量=標準体重×30kcal+付加エネルギー
付加エネルギー(赤ちゃんの成長に必要なエネルギー)
- 妊娠初期(~16週未満):+50kcal
- 妊娠中期(16~28週未満):+250kcal
- 妊娠後期(28週以降):+450kcal
なお、妊娠前から肥満傾向がある場合は、付加量を加えずにエネルギー量を調整することが推奨されるケースもあります。個人の体質や状態に応じて、医師の指導のもと適切な摂取量を把握しておきましょう。
妊婦健診を欠かさず受けましょう
妊婦健診は、妊娠糖尿病を早期に発見するための大切な機会であり、母体と胎児の健康を守るためにも不可欠です。健診スケジュールを守って定期的に通院し、少しでも不安な体調の変化があれば、遠慮せず医師に相談しましょう。
妊娠糖尿病の治療
糖尿病という言葉から重篤な合併症を想像し、不安を感じる方も多いかもしれません。しかし妊娠糖尿病は、適切な治療(食事・運動・薬物療法)を行えば、赤ちゃんへの影響を最小限に抑えることが可能です。医師の指導に従い、無理なく継続できる治療を続けていくことが大切です。
食事療法
軽度の妊娠糖尿病であれば、まずは食事内容の見直しが治療の中心となります。エネルギー摂取量を自分に合った適正な範囲に調整し、栄養のバランスを保ちながら血糖値の急激な上昇を防ぐことが目標です。
- 野菜・海藻・きのこ類など、食物繊維を多く含む食材を取り入れると、血糖値の上昇を緩やかにできます。
- アーモンド、小魚、ヨーグルトなどは、血糖の急変を抑える間食としてお勧めです。
- 一度に大量に食べるのではなく、1日の食事を3食から6回程度に小分けして摂取する「分食」も効果的です。
当院では、患者様それぞれの生活習慣に合わせた栄養指導を行っています。不安な点があればお気軽にご相談ください。
運動療法
一般的な糖尿病の運動療法は妊娠中には負担が大きい場合があるため、妊娠糖尿病の方に適した運動方法を個別にお伝えしています。運動を始める前には、必ず医師と相談しましょう。
以下が安全な運動の目安となります。
- 妊婦向け有酸素運動(マタニティビクス、マタニティヨガ、ウォーキングなど)が適しています
- 運動は食後1〜2時間以内に行うのが理想的です
- 1回の運動は30分以内、週に3〜4回を目安に継続しましょう
- 脈拍が1分あたり140を超えないように注意します
- 体調不良(気分が悪い、息苦しいなど)を感じた場合は、すぐに中止してください
- 水分はこまめに補給しましょう
また、薬物療法中の方は低血糖に注意が必要です。万一に備え、ブドウ糖や砂糖、水分に糖分を含む飲料などを手元に準備しておくようにしましょう。少しでも体調の異常を感じたら無理せず休むことが大切です。
薬物療法
食事や運動による管理で十分な改善が得られない場合は、インスリン注射による治療が選択されます。インスリンは妊娠中でも安全に使用できるとされており、赤ちゃんや母体へのリスクを避けるためにも、早期からの血糖コントロールが求められます。
妊娠糖尿病における低血糖への注意
妊娠糖尿病の治療では、血糖コントロールのために厳格な食事制限が必要になることがあります。このような管理は高血糖を防ぐ効果がある一方で、低血糖を引き起こすリスクも伴います。特にインスリン治療を受けている場合は注意が必要で、低血糖の兆候や対処法を事前に理解し、万が一の際にはすぐに対応できる準備をしておくことが重要です。
低血糖の症状と進行段階
低血糖は、症状の進行により以下の3段階に分けられます。
初期症状
- 冷や汗や不快な汗をかく
- 動悸がする
- 体が火照る
- 手足が震える
- 強い空腹感
この段階であれば、ご自身での適切な対処で回復が期待できます。
意識障害の兆候
- 強い疲労感
- 全身の脱力感
- 強い眠気
- 集中力の低下
- 物が二重に見える
ここまで進行すると、自分で冷静な対応を取ることが難しくなります。
低血糖昏睡
- 意識を失う状態(昏睡)
この状態は非常に危険で緊急対応が必要です。長時間放置されると、母体だけでなく胎児にも悪影響が及ぶ可能性があります。
低血糖に備えるために以下のポイントを意識しましょう。
- ご自身が妊娠糖尿病や糖尿病合併妊娠であることを家族や周囲の人に共有しておく
- サポートが必要なときの対応方法を事前に説明しておく
- ヘルプマークを身につけ、外出時もサポートが受けられるようにしておく
低血糖の対処法
低血糖の初期症状が現れた際には、すぐにブドウ糖を約10g摂取することが基本的な対処法となります。ブドウ糖は素早く吸収され、低血糖の症状改善に即効性があるため、常に携帯し、すぐに口にできるよう準備しておくと安心です。万が一ブドウ糖が手元にない場合は、同程度の糖分を含むジュースや、砂糖約20gで代用することも可能です。ただし、砂糖は体内でブドウ糖に分解されるまでに時間がかかるため、可能であればブドウ糖を使用するようにしましょう。摂取後は15分程度安静にして経過を観察し、症状の改善が見られない場合には、さらに10g程度のブドウ糖を追加で摂取します。症状が落ち着いたとしても、自己判断で済ませず、できるだけ早めに受診してください。
出産後も油断せず、継続的な健康管理を
妊娠糖尿病は、出産によって胎盤が体外に排出されることで、多くの場合は自然に改善していきます。しかし、症状が落ち着いた後も油断は禁物です。妊娠糖尿病を経験した方は、そうでない方に比べて、20〜30年後に糖尿病を発症するリスクが約7倍に高まると指摘されています。そのため、出産後も定期的な健康診断を受け、自身の血糖状態を把握しておくことが重要です。また、糖尿病の発症を防ぐためには、肥満を避けることや、バランスの良い食事、適度な運動といった日々の生活習慣の見直しも欠かせません。産後も継続的な自己管理を意識していきましょう。