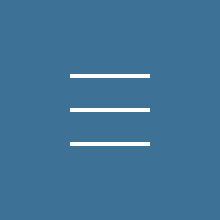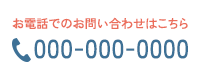過敏性腸症候群とは
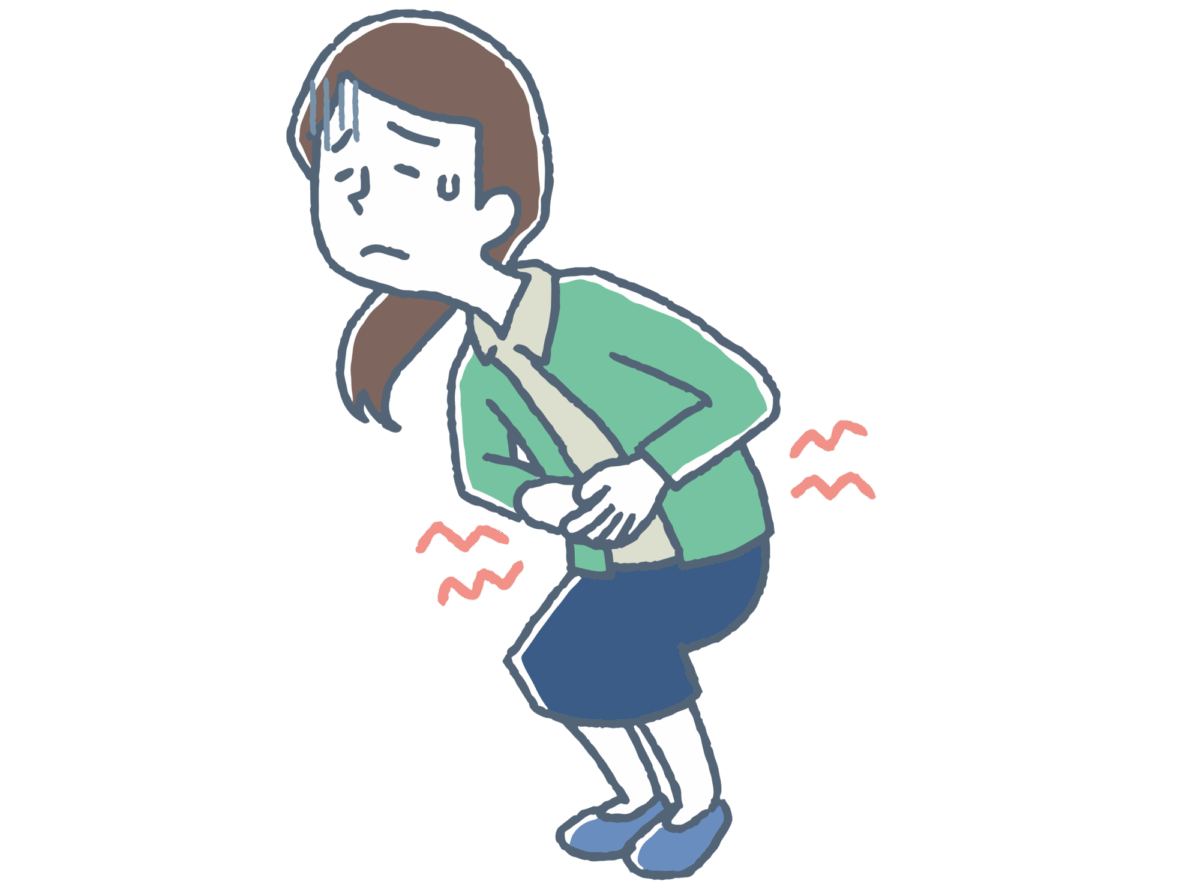 過敏性腸症候群は、下痢や便秘などの便通異常に腹痛を伴い、膨満感やガスによる不快感が長く続く病気です。大腸カメラ検査を行っても潰瘍や腫瘍などの明らかな異常は見られず、精神的ストレスなどによって腸の働きが乱れることが主な原因と考えられています。
過敏性腸症候群は、下痢や便秘などの便通異常に腹痛を伴い、膨満感やガスによる不快感が長く続く病気です。大腸カメラ検査を行っても潰瘍や腫瘍などの明らかな異常は見られず、精神的ストレスなどによって腸の働きが乱れることが主な原因と考えられています。
症状は不安や緊張などの心理的要因で悪化することが多く、排便やガスの症状そのものが新たなストレスとなり、さらに症状を強めてしまう悪循環に陥ることもあります。その結果、生活の質が大きく低下し、仕事や学業に支障をきたすケースも少なくありません。
適切な治療で症状の軽減や改善が期待できるため、気になる症状が続く場合はお早めに当院までご相談ください。
過敏性腸症候群の原因
精神的ストレスなどをきっかけに、腸の蠕動運動が過剰になる・低下するといった機能異常や、腸の知覚が過敏になる状態が生じることで発症します。ただし、こうした腸の機能不全や知覚過敏がなぜ起こるのかという根本原因については、まだ完全には解明されていません。
過敏性腸症候群の症状
過敏性腸症候群は、症状の現れ方によって大きく4つのタイプに分けられます。
下痢型
不安や緊張の直後に急な腹痛が起こり、その後すぐに水様便や軟便が出ます。排便後は症状が落ち着きますが、1日に何度も繰り返すことがあり、特に朝の時間帯に起こりやすい傾向があります。
便秘型
排便が困難で痛みを伴い、硬くウサギのようなコロコロした便が出るのが特徴です。
混合型
下痢と便秘が交互に起こるタイプで、腹痛やお腹の張りなどの不快感を伴います。
分類不能型
上記のいずれにも当てはまらないタイプで、ガスが溜まりやすく腹部膨満感や違和感が主な症状です。
過敏性腸症候群の診断
大腸に潰瘍や腫瘍などの器質的な異常がなく、かつ他の疾患によって症状が引き起こされていないことが確認されたうえで診断されます。過敏性腸症候群と思われていた症状が、実際には、潰瘍性大腸炎などの慢性炎症性腸疾患によるものだった、という例も少なくありません。
そのため、下痢や便秘、腹部不快感などの症状がある場合には、まず大腸カメラ検査を受けることが重要です。大腸カメラ検査や血液検査、腹部超音波検査などで異常が見つからない場合に、国際的な診断基準に基づいて過敏性腸症候群と診断されます。
Rome III基準
- 直近3ヶ月間に、月3日以上の頻度で腹痛または腹部の不快感が繰り返し出現している
- かつ、以下3項目のうち2項目以上に該当する
- 排便によって症状が軽減する
- 症状出現時に排便回数が増える、または減る
- 症状出現時に便の形が柔らかくなる、または硬くなる
※6ヶ月以上前から症状が存在し、直近3ヶ月が上記条件を満たしていることが必要です。
当院では、最新型の内視鏡システムを導入し、より高精度な検査を可能にしています。経験豊富な内視鏡専門医が担当し、患者様の不安や負担を軽減しながら、安全を最優先に検査を行っています。また、ご希望に応じて鎮静剤を用いて眠っている間に検査を受けることが可能です。大腸カメラ検査に関する不安やご質問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
過敏性腸症候群の治療
治療の中心は薬物療法ですが、効果が現れるまでには一定の期間が必要です。そのため、途中で中断せず継続することが重要です。また、再発を防ぐために、食事や生活習慣の見直しも併せて行います。
薬物療法
患者様それぞれの症状や原因に応じて、下痢・便秘・膨満感などのつらい症状を和らげるお薬を処方します。再診時には症状の変化や体調を丁寧に伺い、お薬の種類や量を適宜調整します。
使用するお薬には以下のようなものがあります。
- 消化管の運動を改善するお薬
- 腸内環境を整える乳酸菌や酪酸菌製剤
- 便の状態を整えるお薬
ストレスが症状の引き金となっている場合は、抗不安薬や抗うつ薬が有効となるケースもあります。お薬についての疑問や希望があればご相談ください。
生活習慣の見直し
症状の軽減と再発予防のため、患者様と相談しながら食事内容や生活リズムの見直しを行います。できる限り負担の少ない方法で改善できるよう、細やかなサポートを行っています。
食事療法
- 1日3食を毎日ほぼ同じ時間に摂る
- 栄養バランスの取れたメニューを選び、よく噛んで食べる
- 香辛料・カフェイン・アルコール・脂質の摂りすぎを避ける
- 食物繊維や水分をしっかり摂る
運動療法
軽い運動でも腸の働きや血流、代謝の改善に役立ちます。少し早歩きの散歩程度から始め、日常生活に無理なく取り入れることが大切です。
ストレスケア
過敏性腸症候群はストレスによって悪化しやすいため、十分な睡眠と休養を確保し、心身の負担を減らす工夫が必要です。ストレスを完全になくすことは難しいですが、うまく付き合うことが症状管理の鍵となります。
例えば、入浴でリラックスする時間を確保する、趣味やスポーツなど自分なりのストレス解消法を積極的に取り入れることが効果的です。