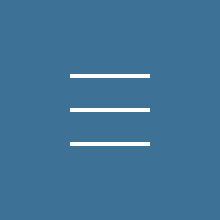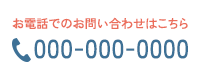尿のにおいは、体からの重要なサインです。当院では、尿のにおいだけでなく、色や濁りなど尿に関する様々なお悩みに対応しています。普段と違う変化に気づいた際は、遠慮なくご相談ください。
尿がにおう原因
 尿のにおいに変化が見られる場合、腎臓から尿道に至るまでの排尿経路に異常が生じている可能性があります。具体的には、尿中に糖分や細菌、がん細胞が含まれることが、においの原因となることがあります。
尿のにおいに変化が見られる場合、腎臓から尿道に至るまでの排尿経路に異常が生じている可能性があります。具体的には、尿中に糖分や細菌、がん細胞が含まれることが、においの原因となることがあります。
尿に糖が含まれている場合
糖尿病の方は、インスリンの分泌異常で血糖がうまく利用できず、代わりに脂肪が分解されることで「ケトン体」と呼ばれる物質が作られます。ケトン体が尿に混じると、甘酸っぱいにおいが発生します。尿から甘いにおいがする場合、重度の高血糖が疑われます。放置は危険なため、できるだけ早く受診してください。
細菌感染によるもの
腎臓から尿道に至るまでの経路で細菌感染が起きると、尿素が分解される過程でアンモニア臭が強くなることがあります。尿が濁る、尿蛋白・尿潜血の異常が見られることもあり、発熱や排尿時の痛みなどを伴うケースもあります。前立腺炎・腎盂腎炎・膀胱炎・尿道炎などが主な原因疾患として挙げられます。こうした症状がある場合は、速やかな検査と治療が必要です。
尿にがん細胞が含まれている場合
腎臓や尿管、膀胱にがんがあると、尿中にがん細胞が排出され、これがにおいの原因になることがあります。尿中のがん細胞は「尿細胞診」という検査で確認できます。通常の尿検査に追加する形で実施できますので、気になる症状があればお申し出ください。
ダイエットや激しい運動の影響
糖質制限などのダイエット中や、過度な運動でエネルギー源として脂肪が分解されると、ケトン体が体内で生成され、それが尿に混じることがあります。その結果、糖尿病と同様に尿から甘酸っぱいにおいを感じることがあります。
肝機能の低下
肝臓は体内のアンモニアを分解する重要な臓器です。肝炎や肝硬変などで肝機能が落ちると、アンモニアが体内に蓄積しやすくなり、尿のにおいにも強いアンモニア臭が現れることがあります。採血検査や腹部超音波検査で肝機能の評価が可能ですので、心当たりがある場合はご相談ください。
食べ物やお薬の影響
食事や薬剤が一時的に尿のにおいを変えることもあります。ニンニク・ニラ・カレー・コーヒーといった食品や、アスパラガスによる硫黄臭がその一例です。また、ビタミン剤・抗菌薬・抗てんかん薬などの薬剤でも同様の現象が起きることがあります。これらは原因物質の摂取を止めればにおいも自然に消えていきます。
尿がにおう場合に行う検査
尿検査
 尿中に含まれる細菌や白血球、尿蛋白、潜血の有無を調べることで、感染や炎症の兆候を確認します。また、がんの可能性がある場合には、尿中にがん細胞が含まれていないかを調べる尿細胞診を併用することもあります。
尿中に含まれる細菌や白血球、尿蛋白、潜血の有無を調べることで、感染や炎症の兆候を確認します。また、がんの可能性がある場合には、尿中にがん細胞が含まれていないかを調べる尿細胞診を併用することもあります。
血液検査
血糖値やHbA1cをはじめ、炎症反応、肝機能・腎機能の状態などを幅広く確認します。必要に応じて、腫瘍マーカーの測定も行い、がんの可能性を評価します。
超音波検査
腎臓・尿管・膀胱など、尿路に異常がないかを画像で確認する検査です。糖尿病腎症が疑われる場合には、腎臓の大きさ(腫大や萎縮)を評価する目的でも活用されます。