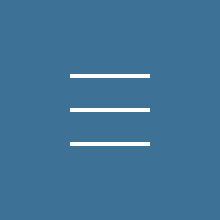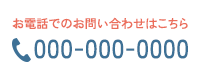ピロリ菌とは
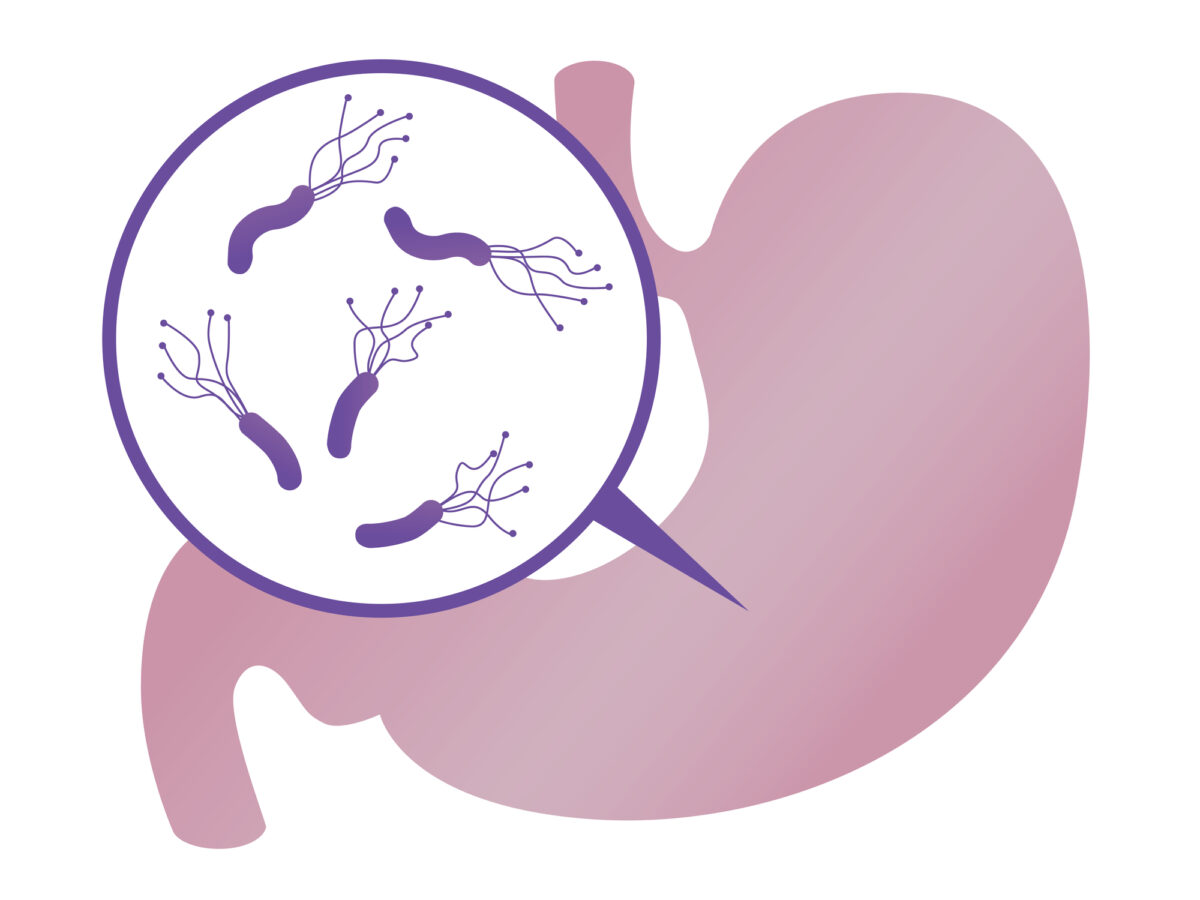 ピロリ菌は、正式には「Helicobacter pylori(ヘリコバクター・ピロリ)」と呼ばれる細菌です。「ヘリコ」はらせん状を意味し、「ピロリ」は胃の出口付近にある幽門(pylorus)から発見されたことに由来しています。この菌はらせん形をしており、複数の鞭毛を持ち、胃酸や消化酵素の存在する環境下でも生き延びる能力を備えています。
ピロリ菌は、正式には「Helicobacter pylori(ヘリコバクター・ピロリ)」と呼ばれる細菌です。「ヘリコ」はらせん状を意味し、「ピロリ」は胃の出口付近にある幽門(pylorus)から発見されたことに由来しています。この菌はらせん形をしており、複数の鞭毛を持ち、胃酸や消化酵素の存在する環境下でも生き延びる能力を備えています。
感染は主に幼少期に起こりやすく、免疫力が未発達な時期に衛生状態が整っていない環境で、井戸水などを介して経口的に体内へ取り込まれることで感染すると考えられています。
ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を分泌して胃内の尿素をアンモニアに変換し、胃酸を中和することで胃内での生存を可能にしています。しかし、この過程で産生される毒素やアンモニアにより胃の粘膜が損傷を受け、萎縮性胃炎を引き起こすことがあります。さらに、萎縮性胃炎が進行すると「腸上皮化生」と呼ばれる状態が生じ、これが一部がん化することで胃がんに発展することも知られています。
国際がん研究機関(IARC)は、世界中の胃がんの約8割がピロリ菌感染と関連していると報告しています。近年、上下水道の整備によって感染率は先進国を中心に低下していますが、日本では依然として高齢層の感染率が高く、80~90%に達するとされます。若年層でも約20%の感染者がいると推定されています。
ピロリ菌に感染すると、胃炎などの症状が現れることもありますが、多くは無症状のまま慢性的な炎症が進行することもあります。そのため、家族に胃がんの既往がある場合は、症状がなくても検査を受けることが望ましいです。感染が判明した場合には、除菌治療によって胃炎や萎縮の進行を抑えることができ、将来的な胃がんリスクの軽減も期待できます。
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌の除菌治療では、2種類の抗生物質に加え、胃酸の分泌を抑える薬剤を併用し、1週間にわたって内服するのが基本的な方法です。胃酸を抑えることで抗生物質の効果を高め、除菌の成功率を高めることができます。
しかし、近年では抗生物質が効きにくい耐性菌も確認されており、初回治療で除菌がうまくいかないケースもあります。その場合には、抗生物質の一部を変更して再治療を行います。初回治療での除菌成功率は85~90%程度ですが、再治療を含めた全体の成功率は97〜98%と高水準です。
また、胃カメラ検査で慢性胃炎が見つかり、ピロリ菌感染が診断された場合には、2回目の再治療までが健康保険の適用範囲となっています。
ピロリ菌の感染検査
胃カメラを用いた検査
迅速ウレアーゼ試験
ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を産生し、胃内の尿素を分解する際にアンモニアと二酸化炭素を発生させます。この過程で起きるpHの変化を検出することで、菌の有無を判定します。
鏡検法
内視鏡で採取した胃の組織を染色し、顕微鏡で直接観察することで、ピロリ菌が存在しているかどうかを確認します。
胃カメラを使用しない検査
尿素呼気試験(UBT)
非内視鏡検査の中で最も信頼性が高いとされる検査方法です。特殊な尿素を含んだお薬を服用し、一定時間後に呼気を採取します。ピロリ菌が存在する場合、お薬に含まれる尿素が分解されて二酸化炭素が発生し、それが吐いた息の中に混ざります。この呼気中の二酸化炭素の量を測定することで感染の有無を判断します。
抗体測定法(血液・尿)
ピロリ菌に感染すると体内で抗体が作られます。血液や尿に含まれる抗体の量を測定し、過去または現在の感染の有無を推定します。
便中抗原測定法
便を採取し、ピロリ菌の抗原が含まれているかを調べる検査です。
ピロリ菌感染検査の保険適用条件
ピロリ菌の除菌には、2種類の抗生物質と胃酸の分泌を抑えるお薬を組み合わせて行う治療法が一般的です。しかし、菌が特定の抗生物質に対して耐性を持っている場合、初回の除菌に失敗することがあります。そのような場合は、使用する抗生物質の一部を変更して、再度除菌治療を行います。
この2回目までの除菌治療は保険の適用対象となっており、初回の成功率は約85~90%、再治療を含めた全体の成功率は97〜98%とされています。ただし、2回の治療で除菌できなかった場合に行う3回目以降の治療は保険適用外となり、自費での対応が必要です。
胃カメラ検査を直近6ヶ月以内に受けた方へ
人間ドックや健康診断などで過去6ヶ月以内に胃カメラ検査を受けており、その際に慢性胃炎と診断された方も、同様にピロリ菌感染検査が保険適用の対象となります。
また、感染が確認された場合には、除菌治療を2回まで保険で受けることが可能です。
ピロリ菌除菌治療の保険適用条件
ピロリ菌の除菌には、2種類の抗生物質と胃酸の分泌を抑えるお薬を組み合わせて行う治療法が一般的です。しかし、菌が特定の抗生物質に対して耐性を持っている場合、初回の除菌に失敗することがあります。そのような場合は、使用する抗生物質の一部を変更して、再度除菌治療を行います。
この2回目までの除菌治療は保険の適用対象となっており、初回の成功率は約85~90%、再治療を含めた全体の成功率は97〜98%とされています。ただし、2回の治療で除菌できなかった場合に行う3回目以降の治療は保険適用外となり、自費での対応が必要です。
ピロリ菌の感染検査・除菌治療に保険が適用されないケース
ピロリ菌の感染検査や除菌治療を胃カメラ検査を受けずに実施した場合、健康保険は適用されず、全額自己負担となります。
一方で、胃カメラによって慢性胃炎の所見が確認された上で感染検査を行い、ピロリ菌陽性と診断された場合には、2回目の除菌まで保険で治療を受けることが可能です。
また、保険診療で使用できる抗生物質は、ペニシリン系の「サワシリン」およびマクロライド系の「クラリスロマイシン(クラリス)」に限定されています。これらのお薬に対してアレルギーがある場合や、他の抗生物質を用いて除菌を行う必要がある場合は、自由診療扱いとなります。
ピロリ菌除菌治療の流れ
胃カメラ検査で慢性胃炎やその他の関連疾患が確認された場合、ピロリ菌の感染検査が行われます。感染が認められた際には、除菌治療がスタートします。
1除菌治療
除菌治療では、2種類の抗生物質と胃酸の分泌を抑える薬剤が処方されます。これらを1週間継続して服用することで、ピロリ菌の除菌を目指します。
ただし、以下のような副作用が現れる可能性があります。
- 肝機能異常(約3%)
- 蕁麻疹(約5%)
- 下痢(約13%)
- 味覚異常(約30%)
これらの症状が見られた場合は、速やかに当院までご連絡ください。さらに、呼吸困難や咳、皮膚の腫れを伴う重篤なアレルギー反応が出た際には、救急対応が可能な医療機関にご連絡の上、すぐに受診してください。
2除菌判定
お薬の服用が終了してから1ヶ月以上経過後に、尿素呼気試験(UBT)などによる判定検査を行います。これは、除菌が成功しているかを確認するための検査です。当院ではUBTの検査は即日結果が出ます。
検査結果で除菌が完了していれば治療は終了ですが、もし菌が残っていた場合には、再度治療を実施します。
32回目の除菌治療
初回治療で使用した抗生物質のうち「クラリスロマイシン」を、別の抗生物質である「メトロニダゾール」に変更し、同じく1週間の服薬治療を行います。治療の流れや注意点は1回目と同様です。
42回目の除菌判定
2回目の治療後もお薬の服用から1ヶ月以上空けて判定検査を行います。除菌が確認できれば治療は終了です。
2回目の除菌治療が失敗した場合、3回目の除菌治療を自費診療で受けることが可能です。保険は適用されませんが、使用できる抗生物質の選択肢が広がるため、より効果的な治療が期待できます。自費治療をご希望の方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
また、除菌に成功した場合でも、長年の感染による胃粘膜のダメージが残っていることがあります。特に萎縮性胃炎が確認された方は、胃がん発症のリスクが高まるため、定期的な胃カメラ検査の継続が推奨されます。今後の検査や経過観察についても、当院で丁寧に対応いたしますので、気になることがあればご相談ください。